カテゴリーアーカイブ: 文章の書き方講座
保護中: 冬の講座(2024年2月24日)
秋の講座(2023年11月25日)の資料
●こちらの2つのファイルが今回の資料です
You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen, but do you recall the most famous reindeer of all?
●参考資料(当日の新潟日報から)

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/syokuhin/r4yusyutujisseki.html
2023年8月26日「夏の講座」資料
2023年5月27日「春の講座」資料
●「春の講座」資料
●以下は参考資料です(印刷不要)
保護中: 冬の講座の資料です
秋の講座の資料
保護中: 夏の講座(2022年8月28日)資料
保護中: 春の講座(2022年5月28日)資料
保護中: 「季節の講座」の資料(2022年2月26日)
保護中: 曲の型当てクイズ3連発(秋の講座)
保護中: 秋の講座(2021年11月27日)の資料
保護中: 季節の講座(2021年8月28日)
保護中: 文章の書き方講座(2021年5月29日)
【文章の書き方】なぜ文章のパワーをモノにしたいのか
●文章の真のパワーをモノにしないともったいない
新潟市でずっと「文章の書き方講座」をおこなっていますが、現在はオンラインで実施しています。
ご自宅でじっくり受講なさってください。
次回は2020年11月28日(土)です。
【オンライン文章講座】(秋の講座)
日時:2020年11月28日(土)15:00~20:00頃
料金:10,000円(税込)
会場:自宅でオンライン受講
講師:齋藤匡章(言語戦略研究所)
内容:人を動かす文章の書き方
文章力は、一生にわたって役に立つ技能です。誰でもタダで平等に使える「言葉」という道具ですが、だからこそ一人一人の言葉の力によって差がつきます。仕事で言葉を使う場面が多い方は、この講座で言語能力を高めて、周囲のみなさまのお役に立ってあげてください。
※お申込みは https://fermata-cafe.com/fer/lesson/seasonal/ からどうぞ
文章もしゃべりも歌も、道具は「言葉」であり、この道具を使いこなすには「練習」が要ります。

料理に使う包丁だって、事務作業に使うパソコンだって、道具はみんな練習でうまくなりますよね。
逆にいうと、「練習をしても上達しない人」はいません。もちろん「適切な練習」という条件付きではありますが……。
心理言語学というマニアックな学問の視点から、あなたに「文章の力」を身につけてほしい、文章力を身につけないとあまりにもったいない理由があります。
それは「言葉には、仕入れも設備投資も要らない」という、おそらくほかにはない強烈な優位性があるからです。
●「仕入れも設備投資も要らない」がなぜ強烈か
「いつか自分で仕事をしたい」という方は大勢います。「好きなことをして食べていきたい」という夢ですね。
ところが、そう甘くない現実も知っている。なにしろ、スタートするのがそもそも難しい。
知識や技術や勇気だけでなく、お金も要る。
あなたがもし、何か商品やサービスを提供しようと思ったら、なんらかの仕入れや設備投資が必要となるでしょう。
これがかなりの額になるわけです。
食べ物を売るには、食材を仕入れる必要がある。陶器を焼いて売るにも、粘土を仕入れる必要がある。
100円を手にするために、30円や50円を先に払わなければならない。しかもその30円なり50円なりが、ちゃんと100円になる保証はない。売れなければ、ゼロ。
シビアですね。
それだけではありません。飲食店を始めるには小規模でも数百万円の機器が要るし、陶器を焼く窯も、電気式の機械で安く抑えたとしても100万円近く。しかも業務用ではないから負荷がかかるとすぐに故障して余計に高くつく。

美容室は仕入れが少ないほうだと聞きましたが、それでも開業時の設備投資は機械設備だけで数百万円。
建物から建てたら数千万円です。テナントに入っても内装工事に数百万円はかかる。
スタートするだけで、ですよ。
オフィス用に物件を借りるとしたら、ただ契約するだけで数十~数百万円が必要です。
商売って、そういうものですよね。
自分で開業すると、そんなシビアな現実に直面することになりますが、会社に雇われて給料をもらっている人が「自分で仕事を始めたい」と思った時、そのあたりの認識が甘くなりがちなのでは、と感じています。
●「能力さえあれば好きに使っていい」という特殊
あなたはもう、「そう甘くない」と知っているかもしれません。
そう、甘いわけがない。
だとしたら、「仕入れも設備投資も要らない」という言葉の優位性がどれほど強烈であり、どれほど羨望の的であり、どれほどありがたいかがよく理解できるでしょう。
言葉そのものを売るのでなくても、言葉を使って何かを売ろうとしたとき、すでにあなたには「言葉」があります。
言葉を使うのに経費はかかりません。家賃も電気代も仕入れ担当者の人件費も宣伝広告費も、何も要らない。
「言葉」というメディアが持つ、きわめて特殊な性質です。
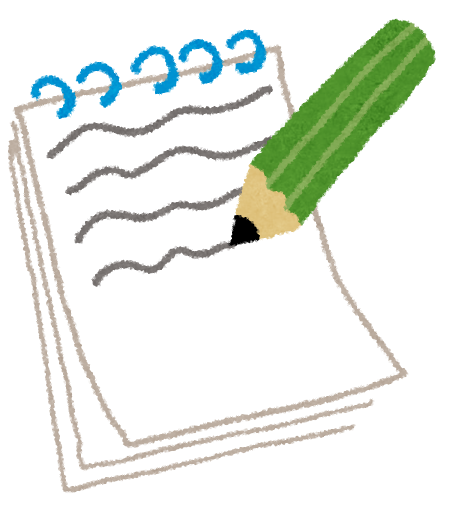
紙と鉛筆さえあればいい。
スマホでもパソコンでも、文章が書ける。
なんなら口で言って書き取ってもらってもいい。
声で録音しておいて、誰かに文字にしてもらってもいい。
そんな自由度の高い材料が、ほかにありますか?
陶器を焼くには、やっぱり粘土でなければいけない。「なんなら小麦粉でも」というわけにはいきません。
「蜂蜜を使うのに、純粋はちみつを仕入れたいが、高いから純粋はあきらめるか」という判断をするかもしれません。
しかし言葉なら、そんな判断は要らない。どんな言葉も、無料です。
しかも、すでに持っている。「どう使うか」の能力さえあれば、好きなものを好きなだけ使っていい。
こんな道具がほかにあるでしょうか。
それが言葉です。
言語能力です。
文章力です。
そこにある道具と材料を、タダで好きなように使って、いくらでも「価値」を作っていい。
とはいえ誰にでも「価値」が作れるわけではない。道具と材料を使いこなす能力があれば、の話。
料理に喩えるなら、調理器具や食材をなんでも好きなだけ使わせてくれて、しかも作った料理は自分で好きなように売っていい。
まるで「錬金術」ですね。
それが文章力です。
「文章力を身につけないとあまりにもったいない」理由がお分かりいただけたでしょうか。
【オンライン文章講座】(秋の講座)
日時:2020年11月28日(土)15:00~20:00頃
料金:10,000円(税込)
会場:自宅でオンライン受講
講師:齋藤匡章(言語戦略研究所)
内容:人を動かす文章の書き方
文章力は、一生にわたって役に立つ技能です。誰でもタダで平等に使える「言葉」という道具ですが、だからこそ一人一人の言葉の力によって差がつきます。仕事で言葉を使う場面が多い方は、この講座で言語能力を高めて、周囲のみなさまのお役に立ってあげてください。
※お申込みは https://fermata-cafe.com/fer/lesson/seasonal/ からどうぞ
* * *
ウェブ:https://wsi-net.org/
メール:tenor.saito@gmail.com
通る声、届く声の出し方の本
新潟市でウクレレ弾き語りを使った社会人向け発声話し方スクール